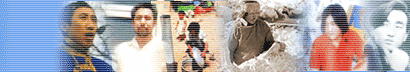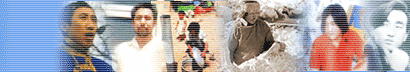|
 |
 |
< 戻る >
「
ソヨルジャブ氏の含羞」
石井英夫(産経新聞論説委員)
しゃべる言葉も、ものの考え方も、はたまたこの世を渡る志も、日本人以上に日本人的なモンゴル人の苦難の半生を追った壮大なノンフィクション――。
主人公ソヨルジャブ氏はダゴール族モンゴル人で、中華民國黒龍江省の草原ホロンバイルの牧民の子に生まれた。満洲国と文化大革命という時代と歴史と政治の荒波に翻弄された運命の所有者だ。長いラーゲリと労働改造所の強制生活を生きぬいて、いま八十二歳。モンゴル人の老日本語教師は今日も静かにほほえんでいる。この人生の長い物語を、感動を抑えずに読み終えることはできなかった。
ソヨルジャブ氏との十数年にわたる交流を、聞き書きで取材した『草原のラーゲリ』の著者・細川呉港(ごこう)氏は、その名が示すように広島は呉市の生まれ(一九四四年)だ。長年、集英社の編集者を務めるかたわら、中国各地を精力的に取材して歩き、東洋文化研究に傾倒してきた。私も一度細川さんに連れられて、ソヨルジャブ氏と内モンゴル自治区の省都フフホトで会ったことがある。それは後述するとして、この人の数奇な運命を追おう。
彼が生まれたのは一九二五(大正十四)年、満洲国ができる七年前だ。ホロンバイルは日本人にはノモンハン事件の戦場として有名で、草原は「風吹草低見牛羊(風吹き、草倒れて、牛羊あらわる)」などと歌われた。難関の国立ハルピン学院を卒業したが、一九四五年八月九日、ソ連軍の満洲・内モンゴル侵攻と満洲国崩壊で、長い悲運の物語がはじまったのだ。モンゴルの戦後史は、ラマ教と人民に対する社会主義の弾圧と粛清と虐殺の歴史といっていい。
ソヨルジャブ氏はモンゴル人民共和国ウランバートル党幹部学校へ留学するが、卒業と同時にモンゴル内務省から「反革命分子」「日本のスパイ」のレッテルを張られ、ラーゲリ(収容所)に投獄されて二十五年の刑を言い渡された。
モンゴルから中国に引渡されたのも束の間、こんどは中国の官憲が待っていて「分裂分子」としてフフホトの牢獄にぶちこまれ、さらにチベット高原の東の端、青海省へ流される。食事も環境も、この世のものとは思われぬ劣悪な生活を強いられ、こうして名誉回復まで実に三十四年の歳月が流れたのだった。
長いラーゲリや監獄に耐えて、自殺することなく生きぬいたのは、自分に正義感と反骨精神があったためだろうと、ソヨルジャブ氏は述懐する。
文化大革命のさ中、仮釈放されて故郷ハイラルに帰ると、中国によって“解放”されたはずの町の名や街路の名が、中国のどこにでもある勝利大街や向華街といった名前に変えられていた。“わが故郷”はなくなっていた。
しかし、町にあふれて熱狂する何万という群衆の前で、自分という一個の人間のなんという小ささ。そして一人の人間の良心や知識が、いかに非力なものであるかを思い知らされたのだった。
ソヨルジャブ氏が友に語った述懐がここにはたくさんつづられているが、そのなかに次のような言葉があり、印象深く読んだ。
「われわれ遊牧民には文化財が残っていない。古い建物がないし、文章がない。民族の歴史を書いた記録がないのだ。ということは文化の伝達や継承がない。だから過去の歴史を振り返り、つぎの時代の礎にしていくことができないのだ」
自らの言葉(文字)で自らの歴史を残さなかった民族の悲哀であろう。
その後、ソヨルジャブ氏はフフホトの外国語訓練センターで、モンゴルの若者たちに日本語を教えた。挨拶に始まって、さまざまな礼儀や謙虚さを教える人間教育をした。
そのころである。私がフフホトで細川さんと一緒にソヨルジャブ氏に会ったのは。
取材手帳を調べると一九九一年の夏だ。端正な顔立ちの氏はこう語るのだった。
「一つの民族がきちんと自立できるかどうか、そのカギは教育です。教育の基本は言葉です」
ソヨルジャブ氏の日本語は完璧だった。いや、日本人以上にみごとな日本語だった。顔のつくりも日本人そっくりだから、何か奇妙な感じがしたのである。
「教育の原型は、日本の江戸時代にあった寺小屋でしょう。教育は手づくりのものでなくちゃならない。私はそういうやり方でやってきました」
驚いた。何しろここは大草原と砂漠が交錯するオルドス台地であり、そう語る人間はモンゴル人なのである。日本の近代化の原点は明治維新ではなく、もっとそれ以前の文化・文政期の塾や寺小屋教育にあるという点でソヨルジャブ氏と私の考え方が一致し、話に思わぬ花が咲いた。
この人によると、日本と蒙古には不思議なほど共通点があるそうだ。教えられてモンゴルの歌に耳を傾けてみると、嫋々(じょうじょう)たる悲哀の調べが日本の追分の旋律にそっくりであることに驚いた。遺伝子や言語学でも多くの類似性があるという。なぜでしょうと尋ねたら、「それがね、なぞです」といって、ソヨルジャブ氏は静かにほほえんだ。
その微笑は、かつて日本人が美風としてきた“含羞”だったのである。
< 戻る >
|
 |
| |
|
 |
|